塔に入った私たちを待っていたのは、想像を絶する光景でした。
レンズであろうもののひとつを塞ぐようにして、それは蠢いていました。「熱喰い」の集合体――竜の熱を吸い尽くし、肥大化した水カビの軍勢です。それは不定形の白い塊でありながら、どこか人の顔を歪ませたような、おぞましい姿をしていました。
集合体は、喉を掻き切ったような、言葉にならない声をあげて襲いかかってきました。
「……っ、来るぞ!」
テイラーの叫びと同時に、私たちは動きました。
まず動いたのはバナナでした。普段のやる気のない態度はどこへやら、彼はしなやかな身のこなしで、石の階段を駆け上がります。
「面倒な相手だ。さっさと焼き払おうじゃないか」
彼は素早く手印を結び、白い塊の周囲に炎のエネルギー円を呼び出します。熱を喰らう性質を持つカビは、その炎さえも吸収しようと、さらに膨れ上がります。
それこそが私たちの狙いでした。
カビが魔法の熱に惹きつけられ、その核の周囲が薄くなった瞬間、テイラーが重い石板を盾にして突っ込みました。彼は石板の端で地面を激しく叩き、氷の破片を散らします。急激な冷却に、熱を溜め込んでいたカビの結合が一瞬だけ脆くなりました。
二人が作った一瞬の隙。私は愛剣を引き抜き、正面から踏み込みました。
私たちの目的はカビを倒すことではありません。その中心にある、複眼システムの起動スイッチを塞いでいる核を断つことです。
私はカビの冷たい粘り気に足を取られそうになりながらも、剣を振り抜きました。
三人の呼吸は見事なまでに合っていました。魔法による誘導、衝撃による凝固、そして必殺の一撃。
切り裂かれた集合体は、断末魔のような凍てついた音を立てて崩れ落ち、さらさらとした無機質な灰へと変わっていきました。
静寂が戻った祭壇で、私たちは肩で息をしていました。
崩れ落ちたカビの灰の中から現れたのは、かつて人であったものの、痛々しく乾いた亡骸でした。彼が最期の瞬間まで胸に抱きしめていたのは、一冊の古びた日記帳です。
私は手袋越しに、崩れそうな頁をそっとめくりました。
日記の冒頭には、かつて「山椒魚派」と呼ばれた彼らが、火口の片隅で小さな幼体たちを慈しんでいた日々の記録が記されていました。
「今日も一匹、無事に脱皮を終えた。その小さな指先を見るたび、いつか彼らが大空を渡る日を夢想せずにはいられない」
そこには、純粋な愛情と、未知の生命への敬畏が溢れていました。
しかし、後半になるにつれ、文字は絶望に歪んでいきます。
仲間の追放。蔓延する水カビ。そして、唯一残された彼自身の、狂気にも似た後悔。
「なぜ、こんなことになってしまったのか。私はただ、あの愛らしい山椒魚たちに幸福になってほしかっただけなのだ。冷たい地下ではなく、星の海を、自由な空を知ってほしかった」
「なのに、私が与えようとした熱は、呪いを育てる苗床となってしまった」
「彼らを救おうと手を伸ばすたび、私の体温は奪われ、指先から白く凍りついていく」
日記の最後は、ひどく震えた文字で、こう締めくくられていました。
「ああ、神よ。もしあなたが本当に空から見守っているのなら。
どうか次の『目』に、私の失敗をなぞらせないでほしい。
私はもう、自分が彼らの救い手なのか、それとも自由を奪う枷なのかさえ、判らなくなってしまった――」
そこで記述は途切れていました。
日記を読み終えたとき、私たちの手元には、勝利の証であるはずの「核」――あの古代人の変わり果てた頭蓋だけが残されていました。功名心に震えていた私の指先が、その時初めて、冷え切ったように強張るのを感じました。
「……やれやれ、これでようやく仕事に取り掛かれるね」
バナナが煤けた髪を払い、面倒そうに、けれどどこか満足げに呟きました。テイラーは解読した石板に従い、塔の壁面に並ぶ「複眼」のレンズ群を調整し始めます。
私はその様子を呆然と眺めていました。穏やかに語りかけてきたあの幻影と、日記に綴られた悲痛な後悔。彼は冷たいカビに覆われ、この塔で何年待っていたのでしょうか。私たちの行為は、果たして彼が望んだ正解に繋がっているのでしょうか。
作業は私の迷いを置き去りにして進んでいきました。バナナは「この微調整こそが、古代人が十五年を費やした知恵の結晶だ」と、いつになく真剣な眼差しでレンズを追い込みます。いよいよ起動という時、私は「待ってくれ」と声を漏らしました。二人は怪訝な顔をしましたが、それは私が必要とした、わずかな溜息の間に過ぎませんでした。
何もしなければ、火山の噴火が人々を呑み込む。私に選択肢などなかったのです。
夜空に浮かぶ神の目――らせん星雲からの微弱な光が、塔のレンズを通じて一点に収束し、火口の竜へと降り注ぎました。 光が触れた瞬間、儀式は魔術から生物学的な変革へと姿を変えます。竜の巨大な細胞核が共鳴し、その身に刻まれた設計図が書き換えられていきました。
その光の奔流の中で、私たちは見てしまったのです。 それは、地球という惑星を「ゆりかご」として利用する、宇宙規模の生命の営みでした。竜たちは火山で熱を蓄え、成体となれば重力を振り切り、あの瞳が待つ星の海へと帰っていく。 古代人が神と崇め、私が功名心のために利用しようとした存在は、ただの渡り鳥に過ぎませんでした。
竜の体表から、白い霜のような「熱喰い」が剥がれ落ち、本来の漆黒の輝きが戻ります。しかし、そこで異変が起きました。
周囲の空へ、星のように輝く光の群れが昇っていくのが見えました。感染を免れ、一足先に旅立つ仲間の竜たちです。私たちの救った竜もまた、力強く翼を広げ、地を蹴ろうとしました。 けれど、その体にはもう、重力を振り切るだけの熱量が残っていませんでした。長くカビに蝕まれたことで、宇宙への片道切符である「熱の貯金」を使い果たしてしまったのです。
私たちは竜を救いました。噴火も止まり、約束通り「誰もが目を剥くような鱗」も手に入れました。 ですが、仲間に置いていかれ、一人この惑星に取り残された竜の咆哮を聞いたとき、私の中の冒険者としての火は、ふっと消えてしまいました。 命を懸けて追い求めた伝説も、富も、名声も。宇宙を渡る彼らの孤独な一生に比べれば、あまりに矮小で、砂粒のようなお遊びに思えてしまったのです。
宇宙山椒魚は、幼年期を終えると地球を離れて宇宙へ出て行く生き物です。 私たちが出会った個体は、地球で長くを過ごしすぎました。先に行った仲間とも、これから飛び立つ子どもたちとも、同じ時を過ごすことはできません。ただ、熱喰いに侵された鱗をふるい落とし、寂しげに吠えるのみです。
テイラーはその鱗を拾い上げ、「ただの寂しい記憶の欠片だ」と吐き捨てました。
帰り道、バナナは面倒そうに別の山へ向かいました。名前を問いかけると、彼は「本名は面倒だ」とポーチから何かを投げてよこしました。それはバナナによく似た、見たこともない果実でした。
……私は、あの日を境に剣を置きました。 世界の仕組みを知りすぎてしまった者の目には、この地上のあらゆる冒険が、ひどく退屈で空虚なものに映るのです。
あの竜の冷たい鱗は、今もグレイスタッドの狩人会場に飾られているでしょう。 あれを見て、あなたが何を感じるか。もし興味があれば、一度行ってみてはいかがでしょうか?

以上のような話を聞いたあなたがたは、
そこにあるという冷たい竜の鱗に興味を持ち、
あるいはギルドからの依頼を受け、
グレイスタッドの街へやってきました。
サンドキャッスルTRPGシナリオ、
『グレイスタッドの冷たい竜の鱗』
はじめていきましょう。
まずは、それぞれキャラクターの紹介をお願いします!
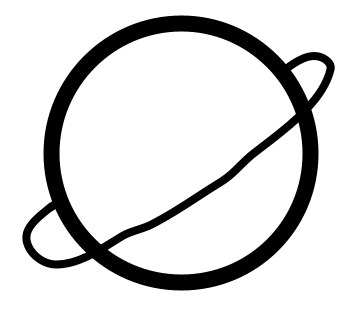


コメント