恐るべき洞窟を抜けた私たちは、まずテイラーの怪我の応急手当を行いました。幸い噛み傷は深くなく、冒険を続けられそうでした。手当を受けながらテイラーは、洞窟の横穴で見つけた石板を見つめています。横穴はほとんど鉱物結晶で塞がれていました。テイラーがなんとか這い進んだ奥には、この石板のみがあったそうです。遺跡が過去の噴火によって溶岩に埋もれて、石板だけが難を逃れたのだろうとテイラーは言います。そして、傷が痛むから少し休んでから行こうと言いました。私は、石板を読みたいだけだろうと思いましたが、それほど急ぐ道でもなかったので休むことにしました。バナナのような名前のエルフは休むなんて面倒だと言うので、では先に行ってくれと言えばそれも面倒だと言いました。私たちは燻製にしたソーセージと、ドライフルーツと、素焼きにしたナッツで少し遅い昼食をとりました。そろそろ行こうと言うと、テイラーがまだ痛むと言うのでもう少し休むことにしました。この日私はドワーフの言う少しと、人間の言う少しが違うことを学びました。声をかけても気が付かないほど、テイラーは石板の解読に集中していましたが、やがて首をかしげてこう言いました。竜とは山椒魚である。その後もぶつぶつ言っているので、一体どうしたんだと声をかけると、石板に書いてあるのだと言います。
「……あらゆる生命のなかで、この者たちはもっとも長大な『生の設計図』を持つ。その糸はあまりに長く、あまりに複雑であり、ゆえに彼らを作り出す細胞のひとつひとつも、他の獣とは比べものにならぬほどに巨大である。 その細胞の中心を覗き込めば、そこには天にある『神の目』と同じ、美しきらせんの紋様が刻まれているのが見えるはずだ。彼らは水に生じ、湿り気とともに歩む小さき隣人であるが、その身の内には星々の巡りと等しき、果てなき時間の蓄積を宿しているのである……」
テイラーはこの部分を読み上げると、ひどく困惑したように顔をしかめました。
「つまり、この石板が言うにはだ。竜の正体というのは、細胞の中に星雲と同じらせんを持っていて、無駄に長い設計図を抱え込んだ、あの湿った場所にいるヌルヌルとした生き物だっていうんだよ」
そんな山椒魚が竜であるとは考えられないので、読み間違えではないかと言いました。あの、井戸の底や湿った岩陰に隠れている、覇気のない生き物が、空を焼き、山を支配する竜の祖先だなんて、あまりにも飛躍がすぎます。テイラーもそのように思い、何度も読み返したようですが、やはり竜は山椒魚だと石板に書いてあるようです。バナナのエルフは、そんなことはどうでも良いから先を急ぐか、野営の準備をしよう、暗くなると面倒だ、と言いました。もし竜が山椒魚であるなら、私の求めている竜の鱗などないのではないか、ここまでの旅路と費用は無駄だったのではないか、と不安になりながらも寝床を準備することにしました。準備している最中に、テイラーが拾った石ころを落としました。目玉のような石ころは地面を転がり、段差に引っかかって止まりました。その目は立てかけておいた石板を見ているようです。すると石板がぼんやりと光り始めました。やがて白っぽい靄を発し、その中から現れたのは、半透明の人形でした。それは「複眼」のシステムを通じ、私たちを見つめて語りかけました。
「旅の方々、初めまして。私は、あなた方の言う古代の民の一人です。……ツィリル様、テイラー様、そしてバナナ様」
突然自分たちの名を呼ばれ、私たちは身を硬くしました。バナナの名前が正確だったかは定かではありませんが。人形は静かに続けます。
「私はすでにこの世にはおりません。ですが、火山の頂にいる竜を救っていただきたいのです。あれは私たちの信仰の象徴であり、世界の熱の源。助けていただけたなら、あなたがたの冒険の輝かしい証となる品を差し上げましょう。飾れば、誰もが目を剥くような珍品です。……何より、今のままではこの火山はやがて冷え、最悪の噴火を招くことになります」
「報酬」と「噴火」という言葉に、私たちは顔を見合わせました。胡散臭さは拭えませんが、ここまで来て手ぶらで帰るわけにもいきません。私は、竜の病について詳しく尋ねました。
「病の正体は、熱を奪う真菌――『熱喰い』と呼ばれる水カビの一種です。通常の薬は効きません。山頂の『螺旋の祭壇』にて、竜の巨大なゲノムを調整する儀式が必要です。そうすれば、竜は変態を遂げ、自らの力でカビを焼き払うでしょう」
「……竜が、変態?」
横で聞いていたエルフのバナナが、面倒そうに口を挟みました。
「竜が山椒魚だってのは、そういうことか。水カビ症なら、マラカイトグリーンでも流し込めば治るんじゃないのか?」
人形は寂しげに微笑んだように見えました。
「ええ、その通りです。私たちの竜は、太古の山椒魚から進化した存在。ですが、その真実を信じる者は少なかった。神の使いとしてきたものが、病気であるとも、のんびりとした両生類であるとも信じたくなかったのでしょう。多くの人々は治療よりも祈祷を選び、私たち山椒魚派を追放したのです。私はこの地で一人、研究を続けてきました。しかし、もはや限界です。未来のあなた方に、すべてを託すしかありません」
この人形は、これまでにも多くの冒険者を見てきたようです。その中で、有毒ガスを恐れず、埋もれた石板を掘り起こしてシステムを起動させたのは、私たちだけだったと言います。
一度戻って応援を呼ぶという選択肢もありました。ですが、この発見を他人に渡したくないという功名心が、私の胸を焦がしました。
「三人でやろう」
私の提案に、バナナは「戻るのも面倒だしね」と肩をすくめ、テイラーは「二人が行くなら……」と石板を抱え直しました。
もし、この選択の先に待つ結末を知っていたなら、私たちは別の言葉を選んでいたのでしょうか。
こうして愚かな三人の冒険者は、白い死の霜が降り始めた山頂へと、足を踏み入れることになったのです。
険しい岩場を登り切り、ようやくカルデラの縁にたどり着いたとき、私たちは思わず足を止めました。そこに広がっていたのは、火山の熱狂ではなく、あまりにも静かな、そして不自然な白銀の世界でした。
竜の熱を奪い尽くそうとする水カビが、大気中のわずかな水分を凍らせ、大地を一面の霜で覆い尽くしていたのです。火口付近の岩肌は、まるで繊細なレースを纏ったかのように白く輝き、生命の鼓動を拒絶しているかのようでした。
「……あれが、私たちの救うべき主だね」
遠く、火口の底に横たわる竜の姿が見えました。
かつて山椒魚が悠久の時を経て進化したというその巨体は、今は力なく、濁った色に染まっています。吐き出される吐息さえもが熱を失い、白い霧となって虚空に消えていく様は、見る者の胸を締め付けます。
背後にそびえ立つのは、竜の民が遺した研究塔です。その壁面には、複眼を彷彿とさせる、無数の精密なレンズが埋め込まれていました。十五年もの歳月を費やして磨き上げられたというその鏡面たちは、長い眠りについていたとは思えないほど、鋭く澄んだ光を放っています。
見上げれば、群青の空には巨大な「神の目」――肉眼では見えるはずもないらせん星雲が、こちらをじっと見つめていました。宇宙の彼方にある巨大な瞳と、この塔にある無数の複眼。そして、竜の巨大な細胞の中に刻まれた、らせんの記憶。
「さあ、始めよう。古代の知恵と、私たちの意思を繋ぐ時だ」
私たちは、霜に閉ざされた塔の重い扉に手をかけました。宇宙の螺旋を地上へ引き込み、竜の生命の灯火を再び燃え上がらせるための、最後の手続きが始まろうとしていました。
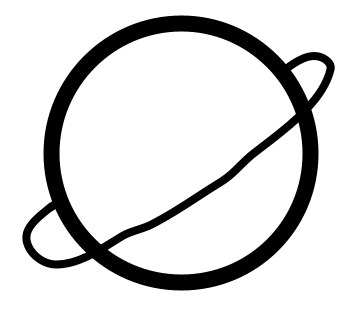


コメント